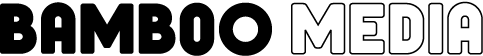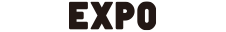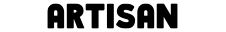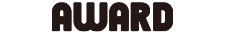写真や印刷、光学、医療機器から、化粧品、再生医療バイオテクノロジーに至るまで幅広い産業分野を手掛ける「富士フイルム」が、東京・南青山に開設した「FUJIFILM Creative Village(フジフイルム クリエイティブ ビレッジ)」。この施設は、同社のデザイナーやITエンジニアを集結し、新しいイノベーションを生む開発拠点だ。その設計に携わったコクヨの青木耕治さんに、計画の経緯や、空間づくりのポイントと共に、これからの働く場のデザインの視点について話を聞いた。
取材・文/BAMBOO MEDIA ポートレート撮影/千葉正人

──本プロジェクトに携わったきっかけについてお聞かせください。
青木:富士フイルムさんとは、8年前から一緒に仕事をさせていただいていて、これまでオフィスを始めとするいくつかの拠点の設計に携わってきました。今回の「FUJIFILM Creative Village」は、デザイン開発拠点である「CLAY」と、IT開発拠点「ITs」という二つの空間で構成されています。デザインセンターに所属するデザイナーたちが集まる「CLAY」を手掛けるのは、今回で3施設目になります。
これら開発拠点を計画する上で富士フイルムでは、単に働くだけのオフィスではなく、“スタジオをつくる”という考え方を持っており、それは企業の考え方や理念が生まれるような場づくりを目指すというものでした。デザインセンターの皆さんと話し合いを重ねる中で、さまざまなデザインの思想が生まれ、ヴァルター・グロピウスの「バウハウス」への共感がテーマとして挙がり、それらが持つ要素も空間づくりに取り入れていきました。

執務エリアの中央を大きな吹き抜けにした大胆なプラン(撮影/山本慶太)
──同施設のデザインにおいて、特徴的なポイントはどういった点でしょうか。
青木:まず、外観を見るとバウハウスの機能主義を思わせる、コンクリートのソリッドなデザインが特徴的です。建築としては一棟の造りですが、「CLAY」と「ITs」の二つの棟に分かれたような見た目になっています。現代のオフィスづくりは、さまざまな部門を一つにまとめる流れがありますが、ここではそれぞれの「スタジオ」を念頭に、そのスタジオ同士が切磋琢磨していくような場にしたいという思いが込められています。

同社が手掛ける分野は多岐にわたり、そのデザイナーの専門分野も異なるが、その分野を超えてデスクを設けることで、社員同士の刺激や緊張感が生まれる(撮影/山本慶太)
一方、建物の中に目を向けると、「CLAY」では、デザインセンターに所属するメンバーが、部門を超えてシャッフルされた席の配置になっています。例えば、カメラのデザインをしている人の隣に、化粧品のパッケージをデザインする人が座っているといった具合です。これは、デザインセンター内で、他の部門がどのようなプロジェクトを進めているのかを日常的に知る機会をつくることで、新しいアイデア創出やイノベーションにつなげていくといった狙いがあります。席の配置は年に一回、部門や役職を超えてクジ引きで決定されます。
もう一つの特徴が、個人のデスクは基本的に壁側に向けて設置した点です。これは、各デザイナーが自分の作業に集中できるようにすると同時に、作業しているPCの画面が常に誰かしらに見られているかもしれないという緊張感をあえて生み出すための仕掛けです。視線は目の前の作業に向けられているけれど、上司や同僚たちからはその姿が見られているという、まさに昔の工房のような環境を企図しています。吹き抜けを通して、誰かに声をかけることもでき、フロアをまたいでの一体感やつながりも生まれています。
また、地階にはバーカウンターを併設した大きなホール空間があり、ここはメンバーが一緒になって何かを企む場所、遊び心のあるクラブのような場所イメージしたつくりです。上階で切磋琢磨し、地階で共創が始まるような場が広がることで、単なるオフィス空間ではない、デザイナーたちが集う“スタジオ”の雰囲気が広がっています。

地下のホール空間は、大きなイベントだけでなく、社員同士のディスカッションや打ち合わせなども頻繁に行われている(撮影/山本慶太)
今回、計画を進める中で、最初にデザインセンターの皆さんとの共通認識として設定したのが「オフィスに安らぎはいらない」という点です。これは、世界のオフィスデザインの潮流とは反対の方向性です。ここでは、休憩やリラックスをするための場所は設けず、職人たちの緊張感が漂うスタジオであることが徹底されています。
同社がここまでストイックにオフィスの計画に取り組み、オリジナリティのある空間づくりに注力できているのには、これまで進めてきたデザイン拠点の成功例が背景にあります。2017年に最初の「CLAY」ができて以降、富士フイルムのデザインセンターでは、以前よりも明らかに、世界のデザインアワードを受賞するような、新しいプロダクトが次々と生み出されていて、その結果から社内でもデザインの重要性を再認識することにつながっていったそうです。デザインセンターの担当の方に言われた、「場がスイッチを入れた。デザイナー達が覚醒した」という言葉が印象に残っています。

デザイナーたちが切磋琢磨する「工房」をテーマとしているため、リラックスする空間よりも、仕事や思考に集中できるような場が点在(撮影/山本慶太)
さらにこのプロジェクトでは、同社のデザインセンターに所属するデザイナー80名が全員参画し、建築から設備、内装、家具、サインといったさまざまな場所やプロダクトを提案しながら進めていったのも特徴です。これらのデザインの交通整理も、私たちコクヨチームの大事な役割の一つでした。また、私たちは人の行動などをもとに空間デザインを考えていくことが多いのですが、プロダクトデザイナーたちのディテールへのこだわりと、それが積み上がっていくような空間づくりに、とても刺激を受けました。一方で、そのさまざまなデザインを一つのオフィスへと落とし込み、機能させていくために、コクヨのオフィスデザインの知見が活かされ、融合し、富士フイルムのデザインセンターらしい空間が出来上がったと感じます。
自分たちのデザインが詰まった場所であり、また、他のオフィスにはないような空間デザインから、社員の愛着も生まれているようです。企業と従業員のエンゲージメントを高めていくことの重要性は、社会的にもよく挙がるテーマですが、「FUJIFILM Creative Village」では、空間づくりとそこに込められたデザインの力によって、会社への帰属意識を育むことに成功していると考えます。
CLAYの地下にあるバーの壁面には、バウハウスのような場となることを目指し、ミース・ファン・デル・ローエの「Der liebe Gott steckt im Detail(神はディテールに宿る)」という言葉が掲げられています。10年、20年とここを拠点に富士フイルムのデザインが生み出されていく中で、未来へ受け継がれていくような同社の理念や思想が育まれ、発信されていくことを願っています。

地下のホールに設けられたバーカウンター背面には、ミース・ファン・デル・ローエの言葉が掲げられている(撮影/山本慶太)
──最後に、「場がスイッチを入れる」ようなオフィスづくりには、どのような視点が重要だとお考えでしょうか。
青木:「FUJIFILM Creative Village」では、スタジオとしての良い緊張感をつくることが、そこで働くデザイナーたちのスイッチになりましたが、これは、それぞれの企業や携わる業務によって異なるものです。私たちコクヨで言えば、世の中のさまざまなオフィスづくりに携わる企業として、自社オフィスを実験場のように捉えて計画しています(掲載参照「THE CAMPUS」)。自らが働く場所で成功したこと、失敗したことを踏まえて、お客様に最適なオフィスの提案ができるよう心掛けています。

コクヨのオフィス「THE CAMPUS」では、実験的な働く空間づくりが試みられている(撮影/ナカサアンドパートナーズ)
また現在、多くの企業で在宅ワークによって若手が社内の知恵や経験を吸収したり、情報を共有したりする機会が減少しているという問題も耳にします。私たちの会社も同じ課題を持っていて、例えば、部門を超えて若手だけが仕事をするフロアを設けて、そこに先輩や上司が顔を出すことで、多くの若手と一緒にコミュニケーションが図れるような試みも行っています。
企業が抱えている課題や目指しているミッションによって、オフィスのつくりは多岐にわたります。その場所において、本当に必要なものが何かを見極め、形にし、多くの企業やそこで働く人が潜在的な力を発揮できるようなデザイン提案を続けていくことが重要だと考えています。
(敬称略)

青木耕治/コクヨ
2007年にコクヨに入社後、椿山荘東京のチャペルVENT VERTやANTE ROOM KYOTO等のホテル設計業務に従事。その後オフィス空間も手掛け始め両分野でreddot best of the best・日本空間デザイン賞KUKAN OF THE YEARなど、国内外のデザイン賞を多数受賞。また空間設計だけに留まらず企画も強みとしており、地域との関係性やカスタマーの行動変容などを軸にファシリティー戦略から空間設計まで包括的なデザインを行っている。また近年はインテリアだけではなく建築や街づくりの一翼を担い、領域をまたぎながら活動の幅を拡げている。
FUJIFILM Creative Village の Interior記事はこちら
詳細を見る